新着情報
- 2013-04-08
- ホームページを更新しました.
- 2013-04-04
- ホームページを開設しました.
研究グループメンバー
以下の文章は、東日本大震災の前後において、私たちの研究グループが実際に経験して蓄積したさまざまな知見が、今後の我が国の身元確認の高度化のために役立つと考えて公表するものです。
目次
- 生体認証から法医学・法歯学そして身元確認へ
- 身元確認の基礎 ~ 法歯学とは?
- 新潟プロジェクト ~ マイルストーンとしての2009年警察歯科医会全国大会
- 東日本大震災2011年3月11日の衝撃
- 東日本大震災における私たちの取り組み
- デジタル歯科情報の標準化とは? ~ 3.11以降の私たちの取り組み
- まとめ
- 謝辞
- 問い合わせ先
1. 生体認証から法医学・法歯学そして身元確認へ
東北大学・大学院情報科学研究科・青木研究室では、生体認証(バイオメトリクス認証)に関して世界トップレベルの研究を推進するとともに、産学連携による実用化に取り組んでいます。私たちは、この研究の一環として、2000年代初頭から法医学・法歯学を支援する情報技術に関する研究を行っています。
大規模な災害や事故あるいは平時における各種の事案が原因で亡くなられた方について、そのご遺体からその方が誰であったのかを特定すること、すなわちご遺体の個人識別のことを、一般に「身元確認」と言います。身元確認は、私たちの社会において、故人と残された家族や仲間の絆を再確認するという重要な意味を含んでおり、「正確さ」と「迅速さ」が求められます。
私たちの日常生活の中で、このような身元確認の実際の取り組みについて注目することはほとんどありませんし、むしろ、ご遺体の話題を取り上げること自体がタブーであるかのように受けとめる傾向があります。しかし、常日頃より、人知れず困難な身元確認の業務に尽力し、亡くなられた方の尊厳を守っている方がいることを心に留めておく必要があります。我が国においては、警察関係者やそれに協力する医師・歯科医師、さらには、法医学・法歯学分野の専門家の皆さんがその役割を担っています。
2. 身元確認の基礎 ~ 法歯学とは?
法歯学(ほうしがく:Forensic dentistry)は、法医学、科学捜査、社会歯科学の一分野であり、犯罪捜査や裁判などの法の適用過程で必要とされる歯学領域の問題を取り扱う学問です。とりわけ身元不明遺体の個人識別は、法歯学における重要なテーマの一つです。歯は、人体の中で最も硬い組織であり、死後も原形を留めて残存する可能性が高いという特徴があります。このため、歯科的な所見は、ご遺体の個人識別においてきわめて有効な情報をもたらします。なお、「法歯学」は「歯科法医学」などと呼ばれる場合もあります。
一般に、損傷の激しい身元不明遺体が発見された場合、その身体のみから個人を特定できる生体特徴としては、指掌紋(ししょうもん=指紋と掌紋のこと)、歯の記録(歯科情報)、DNA型などがあげられます。これらのうち歯科情報は、かなりの確率で歯科医院等に保管されているという点で特筆すべきです。個人識別に用いられる生前の歯科情報としては、歯科診療録(カルテ)、各種X線画像、口腔内写真、歯列模型、技工指示書などがあります。実際の身元確認に際しては、できる限り多くの生前記録を収集・分析し、死後記録と比較することによって個人識別を行います。
このように法歯学的な個人識別の有用性はよく知られており、新聞やテレビなどのマスメディアでも「歯型による身元確認」などと紹介されることがあります。我が国において、この法歯学的な個人識別の重要性が注目された事案として、1985年に、520名もの犠牲者を出した日航機墜落事故があります。この事故においては、総勢約2,800名(延べ人数)の医師・歯科医師・看護師らが、過酷な環境で損傷の激しい遺体の検視・身元確認に協力しました。彼らの献身的な貢献は、事故から四半世紀が経過した今日も記憶に新しいところです。
さて、飛行機事故のような大事故や大災害において、法歯学的な個人識別が有効であることは明らかですが、インシデントの規模が大きくなると、迅速かつ正確に個人を割り出すことが困難になります。これは、遺体の歯牙状態の記録や生前資料の取りまとめ、さらには、それらの突合・照合が、すべて人間の手作業になるからです。つまり、ご遺体が多い場合には、身元確認の膨大な作業全体を、どうしても「人海戦術」に頼らざるを得ないという弱点があります。実際、御巣鷹山の日航機墜落事故を経験して四半世紀経過した後も、歯科的な身元確認の基本的な手法自体は変わっていませんし、特に、情報技術の活用などの議論はほとんどなされていませんでした。
これに対して、私たちの研究グループでは、「将来の大規模災害に備えて、数万人規模の犠牲者を想定した身元確認体制を構築し、その活動を支援する情報システムの整備を進めるべきである」と主張し続けてきました。この主張は、例えば下記の文献に分かりやすく紹介されています。
文献
- 歯科医師による新しい時代の社会貢献へ向けて1「歯科情報データベースと身元確認支援システム」,
Dental Tribune 2009年9月号 - 歯科医師による新しい時代の社会貢献へ向けて2「歯科情報を有効活用した迅速な身元確認の実現」,
Dental Tribune 2009年10月号
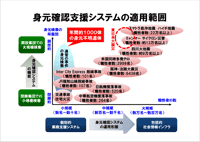
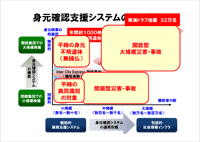
図2-1:災害・事故・事件の分類と身元確認支援システム
(クリックすると図が拡大されます。)
3. 新潟プロジェクト ~ マイルストーンとしての2009年警察歯科医会全国大会
このような私たちの活動に注目し、その主張に初めて賛同してくださったのが、新潟市歯科医師会(当時、松川公敏会長、北村信隆理事)でした。新潟市歯科医師会では、2008年10月30日に、小菅と青木を警察協力医会研修会の講師として迎えて熱心な意見交換を行いました。
この「市」レベルの歯科医師会での真摯な議論は、その後、直ちに「県」レベルの議論に発展しました。その結果、新潟県歯科医師会(当時、岡田広明会長、松﨑正樹専務理事、山下智常務理事)が、ITを活用した身元確認支援技術の将来のあり方を検討するプロジェクト(通称『新潟プロジェクト』)を発足させ、一年以上にわたって議論と検証を重ねました。そして2009年11月14日には、五十嵐治新会長のもと、新潟県歯科医師会が主管した第8回警察歯科医会全国大会が開催され、新潟プロジェクトの初期の成果を全国の警察歯科関係者に広く公表することとなりました。この大会は、それまで、先端的な情報技術とはほとんど無縁であった全国の警察歯科医会の構成員に大きな衝撃を与え、身元確認の高度化・迅速化を図るために情報技術の活用が不可欠であることを初めて広く印象付ける結果となりました。
私たちの研究グループの活動目標である「情報技術を活用した身元確認の高度化」は、この新潟プロジェクトの報告(下記文献)に総括されていますので、ぜひともご一読ください。なお、この新潟プロジェクトの活動は、日本歯科医師会などの協力を得て、現在(2013年3月)も継続しています。
文献
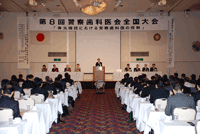
図3-1:第8回警察歯科医会全国大会(2009年11月14日に新潟で開催)
(クリックすると図が拡大されます。)
4. 東日本大震災2011年3月11日の衝撃
前述の新潟プロジェクトの報告を読んでいただけると分かりますが、2009年当時、私たちは、東海・南海・東南海連動型地震などの大災害によって、数万人規模の犠牲者が発生することを危惧し、そのような状況を想定した活動を行っていました。この規模の大災害では、絶対に情報技術の活用が不可欠です。むしろ、はじめから情報技術の運用を前提とした身元確認の組織・体制を確立すべきと考えていました。
将来の大災害の発生に間に合うようにと、一種の焦りのような切迫感を感じながら活動していたときに、東日本大震災が発生したのです。このときの衝撃は、今でも鮮明に思い出されます。しかも、今回の最大の被災地となった石巻市は、研究リーダーの青木にとって生まれ故郷でもあり、愕然といたしました。本当に残念です。このたびの震災により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
私たちの研究グループが、東日本大震災の身元確認チームに参画したのは、2011年の4月末からです。このきっかけになったのが、2009年の新潟での警察歯科医会全国大会において、私たちの提言を熱心に聞いてくださった、宮城県歯科医師会身元確認班の班長の江澤庸博先生との交流です。
東日本大震災では、津波によって亡くなった方が多く、震災当初のご遺体は、その顔貌や着衣、所持品などで確認できる場合が多い状況でした。しかし、その後、1か月を経過すると、ご遺体の損傷が高度になり、顔貌や着衣、所持品での確認が困難になってきました。
宮城県では、震災当初は、手書きのデンタルチャート(ご遺体の歯科カルテ)を中心とした遺体情報収集を行っていましたが、4月に入り、口腔内(こうくうない)のX線画像撮影を含めた、より高度な身元確認手法の導入が必要な状況になっていました。ちょうどそのタイミングで、私たちのグループの小菅が、現地の詳細な様子を聞くために江澤先生と電話で連絡をとり、協力を申し入れました。具体的には、すべてのご遺体を対象とするX線画像撮影、情報システムの導入による身元確認作業の迅速化などについて、私たちのグループの技術を提供することになりました(なお、小菅は、検視警察医であると同時に歯科放射線学の専門家でもあります)。
宮城県における身元確認協力体制を模式的に下図に示します。結果的には、前述の新潟プロジェクトにおいて、江澤先生と知り合ったことをきっかけとして、私たちが身元確認の高度化のために全面的に協力することになりました。
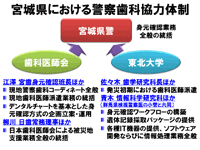
図4-1:宮城県における警察歯科協力体制
(クリックすると図が拡大されます。)
5. 東日本大震災における私たちの取り組み
私たち東北大学のグループは、宮城県警察本部における大震災犠牲者の身元確認作業を支援することを目的として、次のA)~C)に示す取り組みを行いました。なお、これら一連の取り組みは、宮城県歯科医師会の江澤庸博先生および柏崎潤先生(身元確認班班長および副長)、宮城県警察本部の桜井仁志様および伊東哲男様(当時の鑑識課長および機動鑑識隊長)、日本歯科医師会の柳川忠廣先生(常務理事)ほか多数の皆様との共同作業で実施いたしました。改めて御礼申し上げます。
A) 歯科検死標準機材パッケージの整備
私たちは、ポータブルX線撮影装置や、防塵・防水・耐衝撃デジタルカメラ等の歯科検死標準機材の「パッケージ化」の概念を発案し、これに基づく具体的な標準機材パッケージを整備しました。
宮城県においては、震災当初は(1)手書きのデンタルチャートを中心とした遺体情報収集を行っていました。私たちは、これに対して(2)口腔内写真と(3)デンタルX線画像を加えてご遺体の個人識別の高度化を実現し、5月以降に回収されたご遺体に対して(1)~(3)の資料採得を組織的に実施するための体制づくりを行いました。この機材パッケージを運用するためのマニュアル類や各種の記録用紙、実習・訓練のための教材などさまざまな整備を行いました。
最終的には、私たちが持ち込んだ機材と他県から貸与された機材などを含めて、同一仕様の標準機材パッケージを4セット整備して、並列に運用しました。毎日、宮城県警本部から多数の検案所に向けて歯科医師の先生方を派遣する際に、チームごとに標準機材パッケージを携行していただき、チームが帰還する際に機材パッケージごとデータを回収しました。これよって、その日のうちにデジタル画像データを含めて、すべての資料を県警本部に設置した専用の身元確認サーバーに集約することが可能になりました。この身元確認サーバーは、膨大な画像データを取り扱うために、私たちのグループで専用設計を行いました。
なお、歯科検死標準機材パッケージの運用方法はノウハウの塊となっています。これは、他の地域で大規模災害などに備える際の参考になると確信します。

写真5-1:歯科検死標準機材パッケージ
(クリックすると図が拡大されます。)
B) 歯科情報照合ソフトウェアDental Finderの開発
Dental Finder は、災害や事故などによって亡くなられた方の身元確認を円滑、かつ迅速に進めることを目的とした歯科情報照合ソフトウェアです。これまで、私たちの研究グループが東日本大震災の身元確認に取り組む中で、その経験を踏まえて開発・運用を行い、現在、CDの形で無償配布しております(連絡先)。
このDental Finderの主要機能としては、(i)ご遺体の検視(検死)によって得られる歯科情報をデータベースとして管理する機能、(ii)行方不明者の診療録などから得られる歯科情報をデータベースとして管理する機能、(iii)2つのデータベースに格納された歯科情報を照合し、身元の特定に有効な情報を提示する機能があります。
本ソフトウェアは、主として宮城県において、警察および歯科医師会との連携のもと、犠牲者の身元検索のために活用されています。また、岩手県ならびに福島県の警察・歯科医師会にもご協力いただき、被災3県における犠牲者の統合データ(同一形式に変換された歯科情報)に基づく身元検索にも利用されています。
なお、Dental Finderの開発の初期には、宮澤富雄先生(埼玉県開業)のExcelによるスクリーニングモデルを参考にさせていただきました。厚く御礼申し上げます。
Dental Finder が採用する5分類の歯科情報は、震災初期に主として柏崎先生・宮澤先生・江澤先生らの相談で決定されたものです。この表現は、おおむね有効に活用できましたが、運用を進めるに当たり、実際には、この5分類に当てはまらない事例も出てきました。特に、5分類の情報だけではブリッジや総義歯・部分義歯などの情報が表現できないことや、レセプトから読み取った生前記録においてP病名が示唆する「歯牙あり(歯牙の具体的な状態は不明)」という状況が表現できないことなど、いくつかの問題が残りました(現在では、これに対処する工夫を加えて運用しています)。
そこで、Dental Finderの今後の改良方針ですが、歯科情報(生前・死後)の入力形式を、次節6で提案する「標準化されたデジタル歯科情報」のように、通常診療で扱う歯科所見に近い形式に変更する予定です。これにより、さらに詳細な条件の設定に基づく精密な検索が可能になると期待されます。
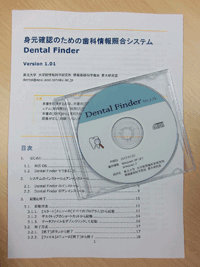
写真5-2:デンタルファインダーのCDは東北大学から無償配布されている
(クリックすると図が拡大されます。)
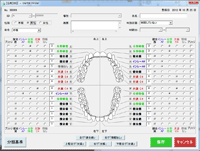
写真5-3:デンタルファインダーの入力画面
(クリックすると図が拡大されます。)
C) 歯科情報に基づく身元確認ワークフローの確立
私たちは、上記のA)歯科検死標準機材パッケージおよびB)歯科情報照合ソフトウェアDental Finderを整備することにより、最終的には下図に示したITを活用した身元確認作業の流れ(情報分野では「ワークフロー」と言います)を確立しました。
さらに、このワークフローを現場に持ち込む際の役割分担をおおむね次のように定めました:
【宮城県警察本部】→ワークフロー全体の管理・統括、
【宮城県歯科医師会】→歯科分野の専門知識に基づく生前・死後記録の収集や最終的な歯牙鑑定、
【東北大学】→情報工学の専門知識に基づく情報機器の整備と各種データの登録・整理・分析。
このワークフローは、今後の大規模災害の歯科的な身元確認を検討するうえで、ひとつのモデルになると思われます。典型的な歯科的個人識別の流れは、Dental Finderの検索によって該当者の候補(生前記録―死後記録のペア)を検索し、その候補に関して、歯科医師が照合・判定用紙に従って異同識別を行うという作業になります。なお、警察ではこの歯科的個人識別の結果を受け取り、その他の多様な特徴(顔貌などの身体的特徴、着衣、所持品、指紋、掌紋、DNA型ほか)も勘案したうえで、総合的に厳密な最終判定を下します。すなわち歯牙鑑定のみで最終判定を下すわけではありませんので留意してください。
また、最近では、DNA型の親子鑑定的手法によって候補者を絞り込んだうえで、歯科医師による歯牙鑑定を行うなどの多様な身元確認の手順が適用されています。なお、警察では、DNA型親子鑑定による候補者の絞り込みのために、歯牙鑑定におけるDental Finderと同様の位置づけのDNA型スクリーニングソフトウェアを利用し、大きな成果をあげています。
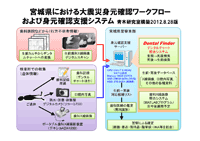
写真5-4:歯科情報に基づく身元確認ワークフロー
(クリックすると図が拡大されます。)
なお、現在の東日本大震災の被害統計は、警察庁のページで確認することができます。 亡くなられた方の身元確認は現在もなお継続中です。ご遺族の皆様のご心中察するに余りあります。私たちは、これからも自分たちの持てる力をできる限りつぎ込んで、警察における身元確認をご支援申し上げる所存です。
文献
- 「身元確認における情報技術の活用」, 宮城県歯科医師会身元確認研修会のスライド, 2012年10月28 日開催.
- 「歯科的個人識別におけるX線画像活用の最前線 ~ 東日本大震災における身元確認の実際と課題」, 月刊インナービジョン, 2012 年1 月号.
- 歯科情報照合ソフトウェアDental Finderのマニュアル.
- 「大規模災害における犠牲者の身元確認と情報技術」, 映像情報メディア学会誌, 2011年12月号.
- 「震災復興と大学 ~東北大学は役割を果たしたか~」, 映像情報メディア学会誌, 2012年3月号.
- 「人を見分ける技術とICT ~産学連携研究の事例から~」, 東北情報通信懇談会会誌 Mercato 85, 2012年Summer issue
- 「大規模災害における身元確認とICT」, ICT ERA (Earthquake Reconstruction Aid) + ABC2012における基調講演, 2012年10月20日開催
- 宮城県警察本部よりの感謝状(平成23年度) 青木, 小菅, 伊藤, 青山
- 宮城県警察本部よりの感謝状(平成24年度) 青木, 伊藤, 青山
- 宮城県歯科医師会よりの感謝状 青木, 小菅
- 防衛歯科懇話会よりの感謝状 青木
- 東北大学大学院歯学研究科よりの感謝状 青木
- 「情報通信月間」東北総合通信局長表彰 青木 表彰式
6. デジタル歯科情報の標準化とは? ~ 3.11以降の私たちの取り組み
東日本大震災によって主として2つの問題が浮き彫りになっています。第一は、警察業務において、歯科情報を活用した身元確認作業のシステム化が立ち遅れている問題です。具体的には、災害時ならびに平時の身元確認業務における歯科的個人識別の活用とIT化の推進(現行システムの改善を含む)、警察と歯科医師会の役割分担の明確化、標準的資機材の整備と訓練などがあげられます。これについては、現在、警察が東日本大震災での経験を踏まえて改善を図っている状況です。
第二は、行方不明者の生前歯科情報の迅速な収集が困難であるという問題です。特に、生前歯科情報の収集およびその分析については、現在のところ人海戦術に頼らざるを得ない状況です。身元確認の現場においては、かかりつけ歯科医院に存在する行方不明者の診療録を入手するために膨大な労力を要しています。また、これらの情報を統一的なデジタルデータ(Dental Finderでは5分類データ)に変換する作業も著しく煩雑です。この問題を解決するために、私たちは、「身元確認のためのデジタル歯科情報の標準化」について提言しています。以下では、これについて基本的な概念を説明いたします。
現在、歯牙鑑定で用いられている情報は、紙書類や写真、フィルム、模型などの、いわゆる、「現物」が中心です。例えば、歯科医院から提供される生前情報としては、カルテやレセプトなどの歯科診療情報、口腔内写真、X線画像(デンタル、パノラマ、CTほか)、模型、技工指示書、問診票などがあります。一方、ご遺体から採取される死後情報としては、デンタルチャート、特徴的歯科所見、口腔内写真、X線画像(主としてデンタル、場合によってはパノラマ、CT)などがあげられます。これらの「現物資料」は、大規模災害などでご遺体が増えると、その取扱いが極めて煩雑になります。現物のままでは、多数の生前資料と死後資料の照合や個人の検索などは事実上不可能です。
これに対して、「デジタル歯科情報のデータ形式の標準化」は、上で述べた「現物資料」に加えて、コンピューターによって蓄積・検索・処理が容易なデジタル歯科情報を定義することを意味しています。これにより、次のような波及効果が期待できます。
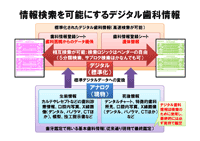
図6-1:歯科情報の標準化
(クリックすると図が拡大されます。)
デジタル歯科情報の標準化によって可能になることの例
- 大規模災害・事故等を含む緊急時における情報提供の迅速化
災害や事故などの発生時に、マークシートやWebなどを介して、行方不明者の歯科情報を、歯科医院から警察へ迅速に提供可能にします。将来は、電子カルテやレセコンから標準的な形式のデータを出力することも技術的には十分に可能です。 - 平時の行方不明者に関する情報提供の効率化
平時の警察業務において、届け出があった特異行方不明者について、当人の歯科情報をかかりつけ歯科医院から迅速に入手可能にします。通常は、行方不明者の届け出を行うご家族等が、かかりつけ歯科医院に情報提供を依頼することを想定しています。 - 歯科情報検索機能を有するカルテ・レセコンの開発 警察から照会された特定の対象者が、自分の歯科医院の患者の中に存在するかどうかを、歯科医師が検索するためのツールを開発できます(カルテやレセコンのメーカーとタイアップします)。
- 患者様向けデジタル歯科情報のお渡し・お預かりサービスの提供
希望する患者に対して、歯科医院からデジタル歯科情報をカードのような形でお渡しする。または、データとしてお預かりするサービスを展開することが可能になります。 - 災害・事故などの緊急時に備えた歯科情報バックアップ事業の展開
歯科医院に存在する貴重な歯科情報が各種の要因によって消失することを防ぐことが可能になります。具体的には、カルテなどの法定保存年限の経過、情報機器の故障、医院の廃業や被災などに起因して歯科情報が消失することを防ぐための歯科情報バックアップ事業を展開できます。 - 歯科健診所見のデジタル保存事業の推進
歯科健診(節目健診、学校健診、職場健診など)の所見についても、標準的なデータ形式でデジタル保存し、災害緊急時に備えることが可能になります。
上記のA)やB)に示したように、データ形式の標準化によって、平時・災害時いずれにおいても歯科的個人識別の大幅な迅速化・効率化が可能です。まず、B)は、平時に警察が行う行方不明者の捜索に対して、有効な捜査情報を提供するものです。これは年間千体を超える我が国の身元不明遺体の解消に有効でしょう。一方、A)の災害緊急時には、この平時業務をスケールアップして大規模に展開することにより迅速に犠牲者を特定することができます。C)は歯科医師の責任による院内個人検索を可能にする技術であり、実現性が高く、現実的な観点から極めて有効であると思われます。D)~F)は、災害緊急時に備えた歯科情報の保存事業であり、将来の身元確認データベースへの足がかりを築くという意味でも意義が大きいと思われます。
ただし、ここで注意していただきたいのは、「デジタル歯科情報の標準化」=「生前歯科情報データベースの構築」ということではないということです。「デジタル歯科情報の標準化」が、全国民の歯科情報を組織的にデータベース化することであると誤解をして反対意見を表明される方がおられますが、特にA)~D)などは国家規模のデータベース化とは全く別次元のことです。これらは、準備が整えばすぐに実施可能です。こういった誤解の多い論点を整理して広く関係者のコンセンサスを得ていくために、現在、日本歯科医師会において柳川忠廣理事を中心としたデータ形式標準化作業部会が設置され、新潟プロジェクトの原案をもとにした検討作業が行われています。今後、できるだけ早く標準化の合意形成を進め、これまでほとんどITの活用が進んでこなかった身元確認の領域において、その高度化・迅速化を図るべきであると考えます。
文献
7. まとめ
私たちは、東日本大震災の以前から、さまざまな媒体を通して大規模災害の犠牲者の身元確認のためにIT の活用が必須であることを訴えてきました。極めて残念なことに、東日本大震災の身元確認の現場において、その主張の重要性を再び強く認識する結果となりました。今後は、この被災経験を決して風化させることなく、関係各位のご指導・ご支援を受けながら、何としても、身元確認技術の高度化を図りたいと切望しています。
また、平時においても、全国的には年間千体以上のご遺体が身元不明として取り扱われています。これらのご遺体の中には、何らかの事件に関与するご遺体が一定割合で含まれていると推測されます。IT による身元確認の高度化は、災害時のみならず、このような平時の犯罪捜査の観点からも重要な取り組みであると考えています。
最後になりましたが、東日本大震災の身元確認の作業は、現在も継続されていることを申し添え、このたびの震災により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
謝辞
東日本大震災における取り組みに際してご協力いただきました。心より厚く御礼申し上げます。
- 宮城県歯科医師会の江澤庸博先生(身元確認班班長)、柏崎潤先生(副長)、さらに、身元確認班の駒形守俊先生、鈴木道治先生、千葉 宏先生、阿部清一郎先生には、常日頃より行動を共にしていただき、並々ならぬご指導を賜りました。また、鈴木敏彦先生には東北大学の歯学研究科を代表して、震災当初から、これまでずっと粘り強くご協力いただきました。宮城県歯科医師会の三宅宏之先生には、石巻で被災されながらも誰よりも多数のご遺体の検死をされ、確認に有効なデータを送ってくださいました。宮城県歯科医師会の佐藤美智子様には、プロジェクトの実行に必須となる膨大なバックヤード事務作業を担当して下さいました。
- 宮城県警察本部の桜井仁志様および伊東哲男様には、発災当時の鑑識課長および機動鑑識隊長として、身元確認における情報技術の活用に関してきわめて迅速かつ合理的な意思決定をされ、全面的なご協力をいただきました。このお二人の存在は、宮城県における法歯学的な身元確認作業の推進において不可欠でした。また、当然ながら、他にも、非常に多数の警察関係者の皆様にご協力いただいております。今後、少しお時間をいただいて、随時、ご紹介差し上げたいと思います。
- 日本歯科医師会の柳川忠廣先生は発災当時の常務理事として、警察歯科活動全体の企画・調整に強力な手腕を発揮されるとともに、政府・中央省庁と被災地との円滑なコミュニケーションを確立していただきました。また、東日本大震災以前より、2009年の新潟での警察歯科医会全国大会のシンポジウムに参画いただくなど、常日頃よりさまざまなご支援・ご指導を賜りました。
- 岩手県歯科医師会の菊月圭吾先生、狩野敦史先生、岩手医科大学の出羽厚二先生には、岩手県における身元確認活動に関する詳細な情報提供ならびに3県統合検索のためのデータ連携に関して、全面的なご指導とご協力を賜りました。
- 宮澤歯科クリニック宮澤富雄先生には、Dental Finderの開発の初期において、エクセルによるスクリーニングモデル参考にさせていただきました。
- 10 DR JAPAN(株)の藤井 彰 社長には、ポータブルX 線撮影装置の導入にご協力いただきました。
- 神奈川歯科大学の川股亮太先生をはじめとする放射線学教室の先生方、さらに、同大学附属病院の閑野政則元放射線技師長には、エックス線撮影の際の放射線防護に関してご指導をいただきました。
- 新潟県歯科医師会の五十嵐 治会長、岡田広明元会長、松川公敏副会長、松﨑正樹専務理事、山下智常務理事、北村信隆先生、瀬賀吉樹様、さらに、松本智宏様をはじめとする株式会社BSNアイネットの関係各位には、新潟プロジェクトの構成員として、身元確認のIT化に関して、大胆かつ粘り強い活動を継続していただき、まさにかけがえのない仲間として支えていただいております。
- 東北大学の大学院歯学研究科の佐々木啓一研究科長をはじめとする東北大学関係各位には、常日頃より何かとご相談させていただき、また、さまざまなご支援をいただいております。
- 秋田大学の大谷真紀先生には、高い専門的な見識と持ち前の明るさ・誠実さを発揮して下さり、異なる県の歯科医師会や法医学者の先生方と、私たちのグループの交流に関して、さまざまなご尽力いただいております。
- 日本大学の小室歳信先生、東京歯科大学の花岡洋一先生、千葉大学の齋藤久子先生、神奈川歯科大学の山田良広先生ならびに山本伊佐夫先生、日本歯科大学の都築民幸先生ならびに岩原香織先生、東邦大学の高橋雅典先生、鶴見大学の佐藤慶太先生をはじめとする法歯学分野の先生方には、平素より懇切なるご指導を賜っております。
- 衆議院議員の古川元久先生ならびに中川正春先生、元衆議院議員の山尾志桜里先生、参議院議員の西村まさみ先生には、歯科情報の標準化事業の実現につきまして、多大なるご支援いただいております。
以上、皆様にこの場をお借りして、改めて厚く御礼申し上げます。
問い合わせ先
本件につきましてご意見やご要望などがございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
青木研究室
東北大学 大学院情報科学研究科
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-05
電話:022-795-7168
電子メール:dental@aoki.ecei.tohoku.ac.jp
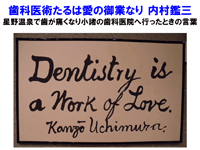
図7-1:内村鑑三の書
(クリックすると図が拡大されます。)